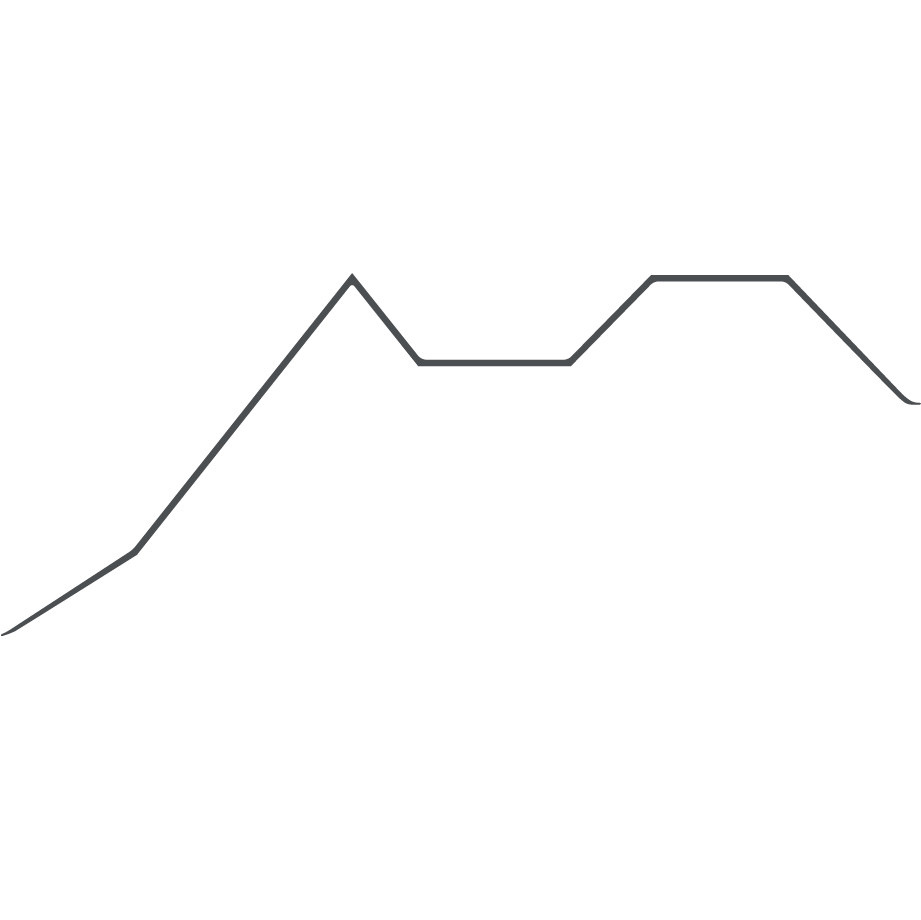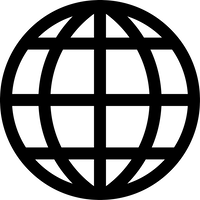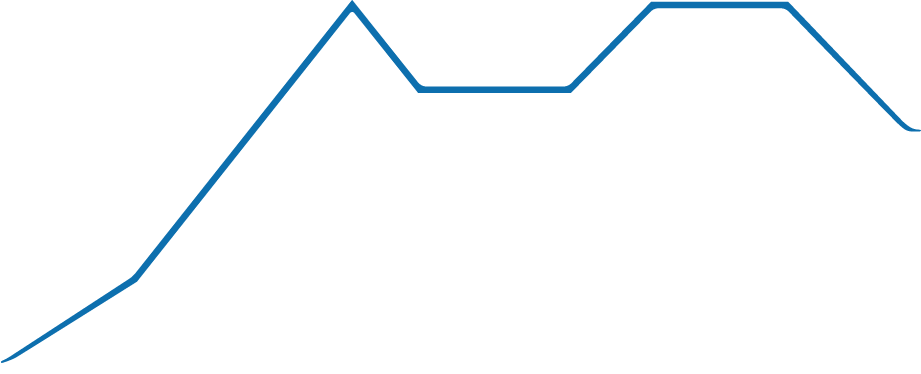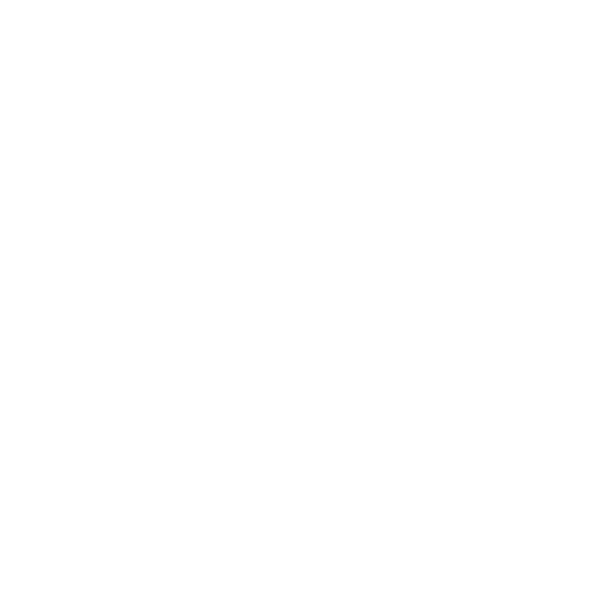ART
アート
建築、注ぎ込む光、瀬戸内海の眺望、料理、現代作家によるミニマル・アートの共演。
アートは、瀬戸内リトリート青凪がご提供できる愉しみの一つです。
自然画家 絵美(しぜんがか・えみ)
1982年愛媛県生まれ。美容専門学校を卒業し、百貨店の美容部員として勤務。途中、美容専門学校のパステル画の非常勤講師を務める。百貨店勤務のかたわらヒト、虫、木々、そして宿るものを描く活動を始める。2021年より 愛媛県各所にて個展を開催。油絵からはじまり アクリル絵の具や、クレヨン画などの画材をとりいれて創作の幅を広げている。幼少期から目には見えない世界を感じることがあり、自然は、さまざまなエネルギーに満ちていることを知る。目では見ることができないモノ・コトを描くことで、本来そこにある尊きモノ、自然との共存を願い伝えていきたい。
渡邊 涼太(わたなべ・りょうた)
2023年に東京藝術大学大学院美術研究科にて修士課程を修了後、東京を拠点に作品を発表。筆で純粋に描く行為と、自身で作成したカッターナイフ等を用いた道具で絵の具を載せて削るという破壊行為を一つの画面で行い、画面にそれらの痕跡を残しながら、作品を制作。筆跡の生々しさ、濃厚さを漂わせるルシアン・フロイドや要素を削ぎ落とし本質に迫ったアルベルト・ジャコメッティなどの実存主義を踏襲し、現代のアプローチへと転換し、キュビズムに通ずる絵画史の更新へ挑戦する絵画技法。

塩出 麻美(しおで・あさみ)
油絵具とアクリル絵具とを用いて厚く描いた静物画に、金網や目の粗い麻布を押し付けて、その結果浮き出てきた絵の具によって作品を作り上げる。絵の具の凹凸によって画面が構成される塩出の作品は、絵画は平面であり、二次元的であるという概念を覆し、2.5次元となる新たな絵画表現及び領域の拡張に挑戦している。
黒瀧 藍玖(くろたき・あいく)
繊維が交差することで立体的な構造が生まれる織物の造形に着眼を得て、手作業を通じた、経糸と緯糸の組み合わせを用いた、立体作品を制作。代表作である、「Human」シリーズでは、鉄の空箱に無数の経糸と緯糸を配置し、その中に人間を配置して作られている。規則的な糸の線で構成されるフレームの中に人間を閉じ込めることで、パターン化された現代社会や人間の思考を浮き彫りにさせる。自身の作品を通じて、空虚な現代社会や彼が捉える人間の視点を浮かび上がらせ、人々をアルゴリズムからの解放へと導くことを試みる。

稲垣 美侑(いながき・みゆき)
東京藝術大学大学院美術研究科美術専攻油画博士号取得後、東京を拠点に作品を制作、発表。「世界はどのような姿をしていたか。」という問いのもと、棲家や庭先といった身近な住環境、自然や動植物が育くむささやかな生態を周期的に観察することにより、対象や場所に内包される記憶や諸感覚を拾いあげ、描く行為を通じて、私たちの生きる場所やその先に広がる景色について問い続ける。流動的かつ多視点的な作品群は、お互いを補完しあいながら展示空間を創出し、ホワイトキューブを唯一無二の「庭」へと変容させる。

小見山 峻(こみやま・しゅん)
神奈川県横浜市出身の写真家、アーティスト。「現実の出来事に対する視点を記録する」という写真の本質を突き詰め、コンピュータによる合成加工などに頼ることなく、グラフィカルな世界を表現、建築する。

ALDO VAN DEN BROEK(アルド・ヴァン・デン・ブローク)
(写真・左)独学のアーティスト。崩壊、変容、再生という儚いサイクルを捉えた作品を制作する。社会の周縁での生活から影響を受け、社会的・政治的・個人的なシステムの無常さと、それらが崩壊する中で生まれるレジリエンスを探求。崩壊とは終焉ではなく、力強さと美が荒廃の中にそっと姿を現す、静かな移行の瞬間を指す。段ボール、木材、金属、布などの時を刻んだ廃材を用いながら、それらの断片に新たな命を吹き込み、重層的で質感豊かな作品へと昇華させる。削り取り、積み重ねるという制作プロセスは、破壊と再生のサイクルを映し出し、傷ついた表面には歴史の重みと再生の可能性が刻まれている。

JOHNNY MAE HAUSER(ジョニー・メイ・ハウザー)
(写真・右)人間の感情が持つ曖昧な存在を繊細に捉えることで知られる、オランダを拠点とするアーティスト。言葉では捉えきれない静寂が宿り、柔らかく、ときにクールな色彩がその独自の世界観を際立たせる。詩的な色使いと匿名性を帯びたイメージを通じて、内省、孤独、そして(感情的な)親密さといったテーマを交差させている。こうして生まれる作品は、作家の内的世界と鑑賞者との間に静かな対話を生み出し、鑑賞者に強制することなく、自然に心に響かせる。

中瀬 萌(なかせ・もえ)
神奈川県藤野町の麓で生まれ育つ。芸術家の父親のもと、幼少期から常に自然と隣り合わせで生活する。自然との関係性に多大なる影響を受けてきた中で感じた景色、匂いや感情を記憶として閉じ込めるように絵画を制作。古代から使われる自然的顔料である蜜蝋を主に用いて、溶融した蜜蝋に色素を混ぜ合わせるエンカウスティークを独学で試みはじめ、現在では自らの方法に発展させながら、国内外で作品を発表している。

FRANK STELLA(フランク・ステラ)
1936年5月12日ボストン生まれ。戦後アメリカの抽象絵画を代表するミニマルアートの作家の一人。画家でもあり、彫刻家。初期には、単純なストライプなどのシンメトリカルな作品を描いていたが、80年代以降は様々な色彩を施し、捻じ曲げられた平面や、2次元の枠を超えて炸裂する絵画とも立体ともつかないダイナミックな作品を制作。

川邊 りえこ(かわべ・りえこ)
日本雅藝倶楽部、にっぽんや工房 主宰。書道家、美術家。日本文化を伝える啓蒙活動として会員制の「日本雅藝倶楽部」を主宰。また1990 年より手掛けている日本の職人によるものづくり、日本の素材を提案する「にっぽんや工房」を運営。2004 年には、「雅藝日本文化交流基金」を立ち上げ、国際交流活動や子供ワークショップを展開。

ひふみ 小野 豊(おの・ゆたか)
1981年、愛媛県生まれ。作庭家。植物空間演出家。招代師。庭、ランドスケープ、山の再生、植物による空間演出、植物アートを手掛ける。自然の原理を基にした植栽デザインをおこない、その土地の神話性や文化を表現し、家、庭、街、山を連動させ、人だけでなく他の生物とも共存できる「場」を作り続けている。

SUIKO(スイコー)
書道に影響を受けた躍動感・生命感のある独自のレタリングを得意とするグラフィティ・アーティスト。2005年に国内初の大規模なグラフィティの企画展「X-COLOR」に参加後、活動規模を拡大しアメリカ、ドイツ、フランスなど様々な国から招待を受け10カ国以上に赴く。グラフィティショップ兼アートスタジオ「dimlight」の代表。

三森 麻理亜(みつもり・まりあ)
日本画家。原料となる鉱石や岩石などを石臼等を使い細かく砕いて粉状にし、一色ずつ一から塗料を作ることも。人生の約半分を海外で過ごした経験から制作を通じて表現したいものは、Borderを超越した多様なものがありのまま存在する世界。日本画を継承しつつ時間や感情など物理的に見ることのできない抽象的な概念を高次元に捉え、可視化させることを試みている。

tsumichara(ツミチャラ)
NFTを活用したアートプロジェクト「BANANA X」の題材は、2019年アート・バーゼル・マイアミで壁に貼られたバナナ「Comedian」。このただ”壁に貼られたバナナ”が620万ドルで落札されたことに着想を得た作品である。現在のNFTムーブメントと「Comedian」を重ねあわせ、NFTを介して当事者としても参加できるようデザインされている。

水上 貴博(みずかみ・たかひろ)
1965年武蔵野美術大学卒業。1980年留学生としてパリに渡り、1982年には狭き門、芸術家認定協会メゾンデアルチストの会員に合格。そして1990年、パリの芸術家著作権協会(A・D・A・G・P)の会員に合格。フランス文化省より国家認定芸術家著作権の有資格を与えられ、国際芸術家として登録される。

PAUL AÏZPIRI(ポール・アイズピリ)
フランスの洋画家。パリ生まれ。1943年パリで初個展を開催して以降、具象画家として実績を積み重ね、1945年パリのサロン・ド・ジューヌ・パンテュール(青年絵画展)の創立会員となる。軽快なタッチと、鮮やかな色彩を好み、静物、風景、人物などのリトグラフで親しまれている。

CASPER(キャスパー)
1996年にグラフィティアートを始めた大阪出身のアーティスト。2013年にREDBULL主催『アメリカ村街路灯アートプロジェクト』の招待アーティストに選ばれる。2000年からは山栄ART工房を立ち上げデザイン業務を開始。FENDIのプロジェクト「F IS FOR FENDI」、MONSTER ENERGY企画でスノーボードメダリスト平野歩夢のX GAMES Aspenミューラルアートに参加。